海の中にはたくさんの生き物が生息していますが、中には陸上で生活している種類と同じような生物がいます。例えば海はウミガメ、陸はリクガメ。海はウミイグアナ、陸はイグアナ。
そして今回の主役であるウミヘビ。陸ではヘビ。この多くが爬虫類であることが多いですが、実は海には爬虫類ではないウミヘビが存在します。

今回は海に暮らす“ウミヘビ”という生き物に着目してお話したいと思います。
ウミヘビとは
どこで見られる?
ウミヘビには鱗があり、爬虫類のため魚のようなヒレは持ちません。世界には約50種類生息していますが、日本で見られるのは9種類ほどです。暖かく浅い海に生活しているので、ダイビングや海水浴でも出会うことがあります。波打ち際の陸にも上がってくることもあります。
水の中での呼吸は?
ウミヘビは水中で呼吸が出来ませんので、水面まで上がり吻先を空気中に出して息継ぎをします。種類にもよりますが潜水時間は30分~1時間以上とかなり長く潜ることができます。なぜここまでの潜水時間を手に入れたのでしょうか?考えられる理由は3つです。
陸上のヘビに比べて基礎代謝量が低く、体内の酸素消費速度が遅い。
ウミヘビの肺は陸上のヘビの肺よりも大きい為より多くの酸素を一度に蓄えられる。
→一般的にヘビには機能する肺が一つしかなく、もう一方は退化しています。これは細長い体に2つの肺を収めることができなくなったと考えられています。体に合わせて肺は細長く、ウミヘビはさらに長い肺をもっています。頭部のすぐ後ろから胴体の後端まであります。長い肺のため体積は大きく、酸素蓄積量も多く長時間の潜水を可能としています。
ウミヘビの血液は陸上のヘビより多くの酸素を含むことができる。
水中に適した体つき
ウミヘビの身体は陸上のヘビに比べて、しっぽが鰭のように薄くなっており左右に動かすことで前への推進力を生んでいます。
コブラ並みの猛毒をもつ
ウミヘビにはコブラ科のヘビと同じような強い神経毒を持っています。ウミヘビに噛まれると噛まれたところから麻痺やしびれが生じて、しばらくすると呼吸や心臓停止となり最悪の場合死に至ります。
しかしウミヘビから人間に向かって牙を向けて襲ってくることはあまりありません。ウミヘビに噛まれたという事故は、ほとんどのケースが人間の方から誤ってつかんでしまったり、子どもが捕まえようとしたりするようなものです。
海でウミヘビを見かけても近づかない、捕まえない、触らない、ということを徹底することがいいでしょう。もしウミヘビに噛まれたら・・・
ウミヘビに噛まれても全く毒が注入されず症状がなく無事に済むことがかなりあります。
毒の症状はすぐに出ず、初期症状で30分ほどかかります。
ウミヘビ専用の解毒剤のようなものはありませんが、病院での対処療法で十分効果はあります。
魚なのにウミヘビ!?

海にすむ“ウミヘビ”という名前の生き物は、爬虫類のウミヘビと魚類のウミヘビがいます。今までは爬虫類のウミヘビの話でしたが、では魚類のウミヘビは一体なんの仲間なのでしょうか?
魚のウミヘビ
実はウナギ目に分類されるウミヘビ科に属する魚をウミヘビと呼びます。実は種類も多く日本全国の海で見ることができます。ほとんどの種類の見た目はウナギに似ていますが、爬虫類のウミヘビにそっくりのシマウミヘビという種類を魚のウミヘビ代表で紹介します。
シマウミヘビは暖かいサンゴ礁域で生活をしています。普段は砂の中や岩の隙間に隠れており、もちろん毒は持っていません。泳ぎ方はヘビと同じように体を左右に蛇行させながら泳ぎます。
見た目は似ててもやはり魚
シマウミヘビはアオマダラウミヘビというウミヘビにそっくりですが、ウナギの仲間の魚です。

ではどこが違うのか見分け方のポイントを紹介します。
一番わかりやすいのは鰭があるかないかです。シマウミヘビには胸鰭、背鰭が小さくありますが、アオマダラウミヘビには鰭がありません。
鰓呼吸をしているかどうか見ると一目瞭然です。シマウミヘビは鰓呼吸をしているので、顔の根本にある鰓が動いています。もちろんアオマダラウミヘビは肺呼吸なので水中で呼吸はしていません。
シマウミヘビの吻先には鼻管といってにおいをかぐ筒のような器官があります。アオマダラウミヘビには鼻管ではなく鼻の穴(鼻孔)があるだけです。
このように海には見た目は似ていても、まったく別の生き物ということがたくさんあります。進化の過程で陸から海へと生活の幅を広げたウミヘビと、魚なのにウミヘビに姿を似せて毒をもつ危険生物と周りにアピールするウミヘビ。呼び名は人間が都合よく付けたものですが、魚のウミヘビはまさか自分がヘビと呼ばれているとは思わないでしょうね。
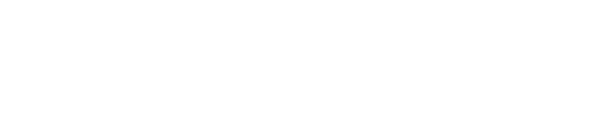









コメント