皆さんは「海老」がどのように育ち我々の食卓まで届いているかご存じでしょうか?
美味しい食事が手軽に食べられる昨今、年末年始や祝いの席での塩焼きや天ぷらは勿論、サンドウィッチや冷凍ドリアまで多くの機会で食べられ日本人に長く愛されている食材、それが海老です。
日本人の海老年間消費量は一人当たり約1.5kgと言われております。そんな当たり前の海老ですが、どのような育ち方をしているかご存じの方はごく少数と感じます。

皆さんの知らないところで多くの壁を乗り越えて日本にやってきている海老について、今回は海外より海老を買い付けていた筆者の経験をもとに、少し垣間見ていきましょう。
よく聞く海老”バナメイエビ”って?
一言で海老と言っても海老には多くの種類があり、その数なんと約2,500種類(文献によっては約2,850種類とも言われています)近くの海老がこの地球上に生息しています。
その中で商業漁獲対象の海老は約180種類あり、有名なところではクルマエビ、ボタンエビ、サクラエビ、イセエビなどが挙げられます。
そんなたくさん種類がいる海老の中で、日本人が主に食べている海老をご存じでしょうか?
そう、バナメイエビとブラックタイガーです。
日本国内海老消費の9割近くがこの2種類で占められており、その中でもバナメイエビは年々シェアを伸ばし、最近では日本消費第一位の海老となりました。つまり意図して避けていない限り一度は食したことがある可能性の高い海老がこのバナメイエビです。
ではバナメイエビはどのような海老なのでしょうか。
学名をLitopenaeus vannamei(Voone,1931)と言い、分類は節足動物門甲殻上綱軟甲綱(エビ綱)真軟綱亜綱(エビ亜綱)ホンエビ上目十脚目根鰓亜目クルマエビ下目クルマエビ上科クルマエビ科Litopenaeus属です。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、このバナメイエビ、なんと美味で有名な海老であるクルマエビと同じクルマエビ科に属しています。
美味しい海老を安定供給したいという思いのもと、クルマエビ科の中でも病気への耐性をもち養殖向けに交配してできた海老がバナメイエビともいわれています。
主要産地は中国・ベトナム・タイなど東南アジアに集中しており、日本はほぼ輸入に頼っています。また2013年に日本各地のレストランでバナメイエビを同じクルマエビ科のシバエビと誤ってメニューに表記したことで食品偽装問題になったこともありました。
それくらい日常の生活に溶け込んでいる海老です。

少し堅い話になりましたが、普段食べている海老の名前がバナメイエビであることが分かればそれだけで他の人より水産通ですので是非とも近しい人に話してみてください。

【獲れたてのバナメイエビ:獲れたては透明】

【加工工場に到着したバナメイエビ:時間経過とともに白色へ】
養殖方法によって旨味が異なる?集約養殖と粗放養殖
バナメイエビについて理解が深まったところで、海老の養殖方法には大きく分けてcheck”集約養殖”と”粗放養殖”の2種類あるのはご存じでしょうか。
集約養殖
バナメイエビの主要生産国であるベトナムでは、主に”集約養殖”といった養殖方法を使われており、人によって完全にコントロールを行い生育する手法です。近しいものとして牛や豚などの畜産をイメージすると分かりやすいかもしれません。
この方法のメリットは多くあり、収穫時期コントロール・外敵からの海老の保護などがありますが、最大の要因は収穫量の見通しが立てやすいという点です。これにより海老の安定供給を実現しています。
しかしデメリットもあり、餌に人口肥料を使うため天然の海老に比べ味が劣るという声もあがっています。
また人による完全コントロールを行うため、pHや含有酸素濃度などの水質管理は確実に行う必要があり、この手間がかかればかかるほど人件費が加算されコストが高くなるという点もあります。
粗放養殖
養殖現場では水質管理の簡便化も求められています。集約養殖と対を成す養殖方法が”粗放養殖”です。
養殖方法は読んで字のごとく、自然の池に稚海老を放ち、時期が来たら収穫を行う手法です。集約養殖と違って人によるコントロールをほとんど行わず、餌も自然に生息しているプランクトンを食べて育ちます。
この手法のメリットは自然環境に近い状態で生育するため味が海老本来の旨味をもつと言われています。
しかし安定供給という面ではデメリットが多く、現在ではほとんどの業者が集約養殖に移っています。ただ一部エリアではブラックタイガーの養殖にこの手法が使われており、僅少ではありますが日本へ輸入も行っていました。

もしもスーパーなどに「粗放養殖のブラックタイガー」があった場合は非常に稀ですので、是非ともご賞味ください。

【集約養殖の海老養殖池:プロペラで酸素を送り込む】
バナメイエビの水揚げは年にたった2回だけ!
日本でよく食べられるバナメイエビですが、生育にどれくらいかかるかご存じの方は非常に少ないと思います。
check特定の環境条件のもと約3か月で成長します。
「水槽を小分けにして時期をずらしていけば一年中海老がとれる」と思われた方もいらっしゃると思いますが、そんなにうまく話は進みません。ネックになるポイントは大きく分けて「養殖池」と「気候」の2点です。
東南アジアの主要養殖国の養殖現場は日本の水槽とは異なり、大きな田んぼのような場所で養殖を行っています。
これを区分けしたり、水槽を用意したりするとコストが跳ね上がるため、現地の養殖業者は好みません。
もう一つネックになるのが「気候」です。
”特定の環境条件”と記載しましたが、ベトナムに当てはめると丁度5~10月の雨季にあたります。この期間の環境でないとバナメイエビは十分に生育しません。
この2点から養殖は5~7月と8~10月の年2回しか行えないのが一般的です。養殖業者たちはこの2回で1年間分を供給しなければなりません。

養殖と言えば安定供給のイメージが強いですが、収穫のタイミングが少ない分、この2回でちゃんと海老を生育させることが養殖業者の腕の見せ所でもあります。

【海老の水揚げ:人の手で池の端から網を閉じて捕獲】
養殖最大の敵!感染症による死滅・気候変動による生育不良
少ない収穫回数の中、海老養殖の最大の関門は「稚海老を出荷までちゃんと育てること」です。
技術が進歩している昨今ではありますが、病気による海老の死滅や気候変動による生育不良は稀ではありません。
直近では2020年10月に沖縄で日本国内初の急性肝膵臓壊死病(AHPND)が確認され、ニュースでも話題に上がりました。
また急性死亡症候群(EMS)と呼ばれる感染症は2009年に中国で初めて確認され、ベトナム、タイ、マレーシア等の東南アジアに広がっており、現在でも確認されています。
また雨季の東南アジアではスコールが起こるたびに養殖池のpHが変動し、そのまま放置すると海老の生育に影響を及ぼします。
感染症の確認やpH維持にも水質管理は大切であり、手軽に水質管理が行える投げ込み式の多項目測定器は養殖業者にとって重要な道具でもあります。
いかがでしたでしょうか
病気や環境リスクと戦い、年に2回しかない水揚げを無事成功して日本へ輸入されてくる海老。
飽食の時代に普段何気なく食べている海老ではありますが、安定供給の裏側には生産者たちの思いがたくさん詰まっています。

次に食べる機会には多くの壁を乗り越えてやってきた海老たちに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。




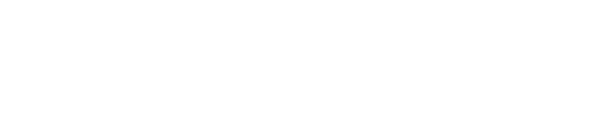






コメント