私は管理栄養士・ケアマネージャーとして、長年「食べることが難しい方々」のサポートをしてきました。しかし、どんな病気も「実際になってみないと本当の大変さは分からない」と痛感しています。
摂食・嚥下について理解していたつもりでも、実際に顎関節症を経験すると、これまで気づかなかったことがたくさんありました。この経験を忘れないよう記録し、顎関節症や虫歯で悩む方々、さらには介護食の分野でも役立てていただければと思います。
「食べられない」理由は人それぞれ違います。
私の場合、顎の痛みで咀嚼が難しく、唾液の分泌が減ってしまったことで、食塊(しょっかい:そしゃくして飲み込みやすい状態になった食べ物)をうまく作れなかったり、味を感じにくくなったりしました。さらに、食後の消化不良やストレスによる偏食にも悩まされました。こうした食事内容は、顎関節の炎症を悪化させる要因にもなります。
顎関節症はすぐに治るものではありません。そのため、一時的な「食べやすさ」だけでなく、「栄養」と「ストレスケア」にも配慮することが大切だと感じています。
本記事では、具体的にどんな食事を選べばいいのか、詳しく解説していきます。
噛めないときの「主食」について
病気中の食事といえば、おかゆが定番です。ただし、食べ物をすりつぶせない状況では、おかゆの米粒でさえ、食べるのが辛い状況。食後に胃の不快感が続きます。ではどうすればいいのでしょうか?
「三分がゆ」よりも「やわらかいおかゆ」がいい
咀嚼嚥下を考える時に、全がゆをおもゆや三分・五分がゆにすることが多いです。しかし、おかゆを炊くときに気をつけるべきは、お米の量ではなく、おかゆの炊き方です。お米はあらかじめ半日から一日水につけておくことで、米の中心まで水分がしっかり入り、炊き上がりがやわらかなおかゆになります。
雑炊、おじや、お茶漬けではダメ?
炊いたご飯から作る雑炊やおじや、お茶漬けは、一見やわらかく食べやすそうに見えます。しかし、米粒の硬さは残っているため、噛まずに飲み込もうとすると丸呑み感が強く、胃への負担が大きくなります。大切なのは水分があるかどうかではなく、米自体がやわらかいかどうかです。とはいえ、米飯よりは米粒がやわらかくなって食べやすいと思います。
フレンチトーストのすすめ!クレープ生地も◎
ハード系のパンは、顎関節症のときにはもっとも食べにくいものの一つです。一方で、クロワッサンのように、少しの力でクシャっと潰れるパンは比較的食べやすい傾向にあります。
さらにおすすめなのがフレンチトーストです。食パンを卵とミルクを混ぜた液にたっぷり浸して焼くことで、歯がなくても口の中で、ほどけるほどやわらかくなります。甘いものが食べたい欲求を満たしながら、卵とミルクでタンパク質も補えるのがメリットです。
また、私がよく食べたのがクレープです。ごく薄く焼いた生地は、噛み切れなくても自然に破けるため、顎への負担が少なく食べやすいのが特徴。なお、ライスペーパーやトルティーヤは噛み切りにくいため不向きです。
噛めないときの「食事形態」について
顎に負担の少ないスープやポタージュは、確かに食べやすいですが、毎日液体ばかりでは食欲もわきません。「固形物を食べたい」という欲求が強くなることもあります。しかし、噛み切れない食材を無理に丸呑みすると、消化不良が続き、体調不良にもつながります。固形物は「きざみ食」にすると食べやすくなります。では、きざむだけで食べやすくなるのでしょうか?
きざみ食は「やわらかい」のがマスト
顎関節症で痛みが強いと、想像以上に丸呑みすることが多くなります。細かくきざんだ食材でも硬いままだと、消化に負担がかかり、胃もたれの原因になります。そのため、「細かくする」だけでなく、「やわらかく調理する」ことが大切です。
きざみ食は「とろみあん」で飲み込みやすく
パラパラとバラける食材は飲み込みづらいため、 片栗粉などのとろみあんをかける と格段に食べやすくなります。また細かく刻んだサラダは、マヨネーズや乳化ドレッシングでまとめると食べやすくなります。マッシュしたジャガイモやカボチャと和えるのもおすすめです。
茶碗蒸しは「具なし」が◎
喉越しがいいプリンや茶碗蒸しはツルリと食べやすいものの一つです。ただし、鶏肉やかまぼこ、しいたけ、銀杏などの固形物が入っていると一気に食べづらくなってしまいます。私たちは、普段の状態であれば、さまざまな食感の食材が混ざりあっている料理でも、食材ごとにしっかり食べ分けることができます。しかし、上手に噛めない状況では、普段当たり前のようにしている機能ができません。
私が顎関節症の痛みがある中で、よく食べたのが、駅の立ち食いそば屋さんのカレー南蛮です。これも茶碗蒸しとも同様です。やわやわのそばに、とろみのついたスープは飲み込みやすく、食べやすいものでした。またカレーの香りは消化を促して、濃いめの味付けとともに食欲が沸きます。ただし、キャベツやねぎなどの葉物野菜や、薄切りの豚肉や細切れの鶏肉、きざんだ油揚げが入っていると、とても食べづらくなります。自分で作るのであれば、ネギも入っていない具なしのカレーそばに、卵だけ落としたものがベストだと思います。食物繊維が補いたいなら、とろろ昆布がおすすめです。
噛めないときの「タンパク質」チャージについて
噛むのがつらいと、パンや麺類、甘いものなどのやわらかい食品に偏りがちになります。しかし、糖質の過剰摂取は 炎症を悪化させ、顎関節症の痛みが長引く 可能性もあります。
また、肉や葉物野菜が食べづらくなるため、タンパク質や食物繊維が不足しやすくなります。そこで、 栄養バランスを整えながら食べやすい食品 を選ぶことが大切です。乳製品や大豆製品、卵は食べやすいタンパク質食品です。また肉や魚類には、食べやすくする工夫が必要です。
食べやすいタンパク質No. 1「温泉卵」
卵は ビタミンCと食物繊維以外のすべての栄養素を含む「完全食」 です。特に 温泉卵 は、咀嚼しなくてもつるっと食べられ、消化の負担も少ないためおすすめ。私はありとあらゆる料理に卵をプラスしていました。
不足するビタミンCや食物繊維は、スムージーなどで補うとよいでしょう。また、このような時は無理をせずに、マルチビタミンのサプリメントを活用するのもいい方法です。
魚や肉を「やわらかく食べやすく」する方法
魚なら、焼き魚よりも煮魚が◎。刺身は噛み切れませんが、ネギトロやサーモンのたたきも食べやすいです。卵黄と絡めてユッケにするとするりと飲み込みやすいです。一方、タコやイカ、エビ、貝類などはどう加工しても食べやすくなりません。
肉料理では厚切り肉は噛み切れず、薄切り肉でも難しいことも。肉類で何とか食べられたのが豆腐ハンバーグです。二度挽きした鶏肉に豆腐を混ぜて作りました。これを一口大よりももっと小さくカットして食べました。丸呑みではありますが、久々にお肉を食べた時は感動しました。また痛みが和らいできた頃に食べられたのが、塩麹漬けの鶏肉。繊維が柔らかくなり、想像以上に食べやすくなりました。食後の消化負担を減らすことにもつながります。
おすすめしたいのが鉄分とともにタンパク質やビタミンも多く含まれている、やわらかく食べやすいレバー。鶏レバーはレバーペーストに、豚や牛のレバーは薄くスライスして、ニラやキャベツ、玉ねぎなどの野菜は使わずに単独で焼くのがいいでしょう。レバー焼きは野菜があるだけで食べづらくなってしまいますので注意しましょう。
「豆乳 → 豆腐 → ひきわり納豆」痛みレベルに合わせた大豆製品の活用
大豆製品は、噛む力に応じて選びやすい食品です。
液体なので、どんな状態でも飲みやすいのが豆乳。痛みがひどくても食べやすい固形物が豆腐。意外と噛みづらいため、痛みが少し落ち着いてから取り入れるのがいいのが、ひきわり納豆。納豆は食物繊維も摂れる植物性のタンパク質です!
まとめ
食事は、栄養を摂るだけでなく、楽しみや生活の質にも深く関わるものです。栄養の偏りはストレスを助長するため、無理のない範囲でマルチビタミンやアミノ酸などのサプリメントを取り入れるのもひとつの手です。
「食べやすさ」だけでなく、消化のしやすさや栄養バランス、おいしさにも配慮した“ストレスケア食”を心がけることが、顎関節症と付き合ううえでも大切だと感じました。
痛みが思うように引かず、「本当に治るの?」と不安になることもありましたが、その不安やストレス自体が、症状を長引かせていたのかもしれません。だからこそ、心も体も無理をせず、自分にやさしい選択を積み重ねていくことが、回復への近道なのだと思います。
プロフィール

GLOCAL EATs
ソーシャルデザイナー 石松 佑梨(いしまつ ゆり)
サッカー日本代表選手をはじめ、世界で活躍するトップアスリートの専属管理栄養士として食トレを提供する。次代を担うジュニアアスリートの食育にも力を入れる。近年では雑誌や商品、レストランなどの栄養監修に携わる一方で、絵本作家としての活動に注力している。
著書:過去最強のコンディションが続く 最強のパーソナルカレー(かんき出版)
インスタグラム:personal_curry
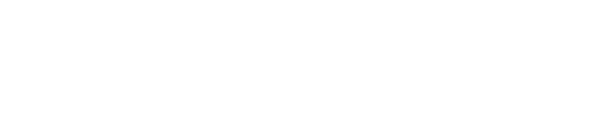




コメント