私は管理栄養士・ケアマネージャーとして、食べられない方々のケアに長年携わってきました。病気や機能的な問題で食事制限が必要になることもありますが、どんなときでも「おいしく食べてほしい」。これは私自身の強い願望でもあります。
摂食・嚥下については専門的に勉強してきたつもりですが、「なってみないと分からない」と痛感することも多々ありました。実際に顎関節症を経験し、新たに気づくことがたくさんあったため、その記録を残しておきたいと思います。同じように顎関節症(がくかんせつしょう)や虫歯で悩んでいる方はもちろん、介護食の分野でも役立てていただければ幸いです。
本記事(第1章)では「顎関節症の基本」について、次回の記事(第2章)では「具体的な食事法」について解説します。
顎関節症とは何か?
顎関節症とは、顎の関節や咀嚼筋(そしゃくきん:噛むときに使う筋肉)に異常が生じる疾患です。噛み合わせの問題やストレス、生活習慣など、さまざまな要因が関係しています。
私の場合、30代前半で親知らずを抜いたことがきっかけで噛み合わせが変わり、顎を動かすとカクカクと音がするようになりました。しかし、痛みがなかったため放置していました。それから10年以上が経ち、ある朝突然、右顎に激しい痛みが発生。歯を噛み締めることができず、食事もままならない状態に…。耳鼻咽喉科を受診したところ歯科での診察をすすめられ、「顎関節症による痛み」と診断されました。
主な症状
• 顎が痛む →口を開けると痛い、噛むと痛い
• 口が開きにくい →大きく開けられない、引っかかる感じがする
• 顎を動かすと音がする →カクカク、ゴリゴリといった音がする
原因
• 噛み合わせの問題 →歯並び、詰め物や被せ物の影響
• 歯ぎしり・食いしばり →ストレスや癖によるもの
• 姿勢の悪さ →猫背やスマホの長時間使用など
• 顎の使いすぎ →硬いものをよく噛む、よく話す、ガムを頻繁に噛む
対応策
• セルフケア →顎のストレッチ、温める、マッサージ、硬い食べものを避ける
• 生活習慣の見直し →姿勢を正す、ストレス管理をする
• 歯科・口腔外科での治療 →マウスピースの使用、噛み合わせの調整、理学療法 など
なんで「食べられない」のか?
私は管理栄養士なので、得意分野は「食べやすい食事」への対応です。
ただし、それを考える前に自分の今の状況について、客観的に知っておく必要があります。「食べられない」と言っても、その理由は人それそれ異なるからです。まずは自分の「食べられない理由」を知ることが第一歩です。
• 顎関節症の痛みで口が開かない
• 虫歯による歯の欠損で噛めない
• アレルギーで食べられない
• 胃もたれや便秘で食欲がない など……
「食べる」動作を考える
さらに「自分のできない動作」を具体的に探りましょう。
「食べる」ことには、さまざまな動作が関わっています。普段は意識しなくても、食べ物や料理によって自然と使い分けています。しかし、何らかの障害があると、複数の動作に影響が出て「食べられない」状態になることがあります。
1. 食べ物を認識する(目で見る)
2. 口に入れる(手や道具を使う)
3. 噛み砕く(歯と顎を使う)
4. 唾液を分泌する(消化を助ける)
5. すりつぶし、食塊を作る(舌を使う)
6. 喉へ送り込む(舌と咽頭の動き)
7. 飲み込む(嚥下する)
8. むせずに食道へ通す(安全に飲み込む)
9. 味や香りを感じる(舌や鼻でも認識する)
10. 胃に届き、消化が始まる(消化器が働く)
まずは、食べるためにどのような動作が必要なのかを知り、今の自分が「できないこと」を具体的に把握することが大切です。そうすることで、適切な対策を見つけることができます。
私ができなかった「食べる」動作
たとえば、顎関節症の痛みで私ができなかったのは、食べ物を噛み砕くことや、すりつぶすことでした。ところが、噛むことができなくなると唾液の分泌量が減り、食塊を上手に作れなかったり、味を感じにくくなったりもしました。
唾液には、食べ物の成分を溶かして味蕾(みらい:舌の味を感じる器官)に届ける役割があります。唾液が少ないと、味の成分がうまく広がらず、味蕾に届きにくくなるため、味を感じにくくなります。また、唾液に含まれる酵素は、デンプンを分解して甘みを引き出す働きもしています。唾液が減ると、消化がうまく進まず、甘みを感じにくくなることもあります。
このように、食べるための動作は 連動 しています。だからこそ、 「今の自分がどの動作をうまくできていないのか」 を知ることが、食べる力を改善する第一歩になります。
二次的な影響について
さらに、顎関節症は「痛くて噛めない」だけではなく、体や心にさまざまな影響を及ぼします。例えば、噛み合わせの変化や顎の緊張が続くと、肩こりや頭痛につながることがあります。
ここでは、管理栄養士の視点から「食事」や「栄養」に関する二次的な影響について解説します。
消化不良のリスク
噛む力が弱まると、食べ物を十分に咀嚼できず、丸呑みしがちになります。高齢者の場合は窒息のリスクがありますが、若い世代でも問題は深刻です。
咀嚼回数が減ると、胃腸への消化負担が増加。未消化の食べ物が腸内環境を悪化させ、便秘や肌荒れの原因にもなります。胃が重い状態が続くと、食欲不振にもつながります。
糖質過多による炎症の悪化
顎が痛むと、柔らかくて食べやすい食品ばかりを選びがちになります。しかし、手軽に食べられる食品には、おかゆや麺類、ケーキ、プリン、シュークリーム…… というように糖質が多いものが多く、栄養バランスが崩れやすくなります。
糖質の過剰摂取は炎症を悪化させるため、顎関節の痛みが長引く原因にもなります。一方で、噛み切りにくい肉類や葉物野菜は避けがちになり、タンパク質や食物繊維が不足することも問題です。
精神的な影響
痛みが続くと「このままずっと食べられないのでは?」と、不安やストレスが募ります。私の場合、医師から「1週間ほどで痛みは落ち着く」と言われましたが、改善しないどころか悪化しているように感じました。
食事の楽しみがなくなり、ストレスが溜まることで甘いものへの欲求が増えることもあります。また、顎の痛みや違和感から会話を避けるようになり、外出の機会が減ることも特徴です。
まとめ|食事の楽しみを取り戻すために
顎関節症による影響は、食事だけでなく体全体に広がることを意識し、早めの対策を取ることが大切です。次の記事では、痛みを軽減しながら栄養バランスを整える食事の工夫について詳しく解説します。
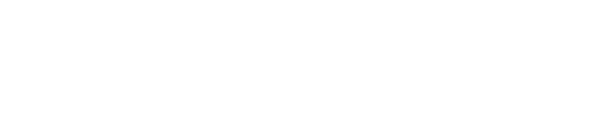





コメント